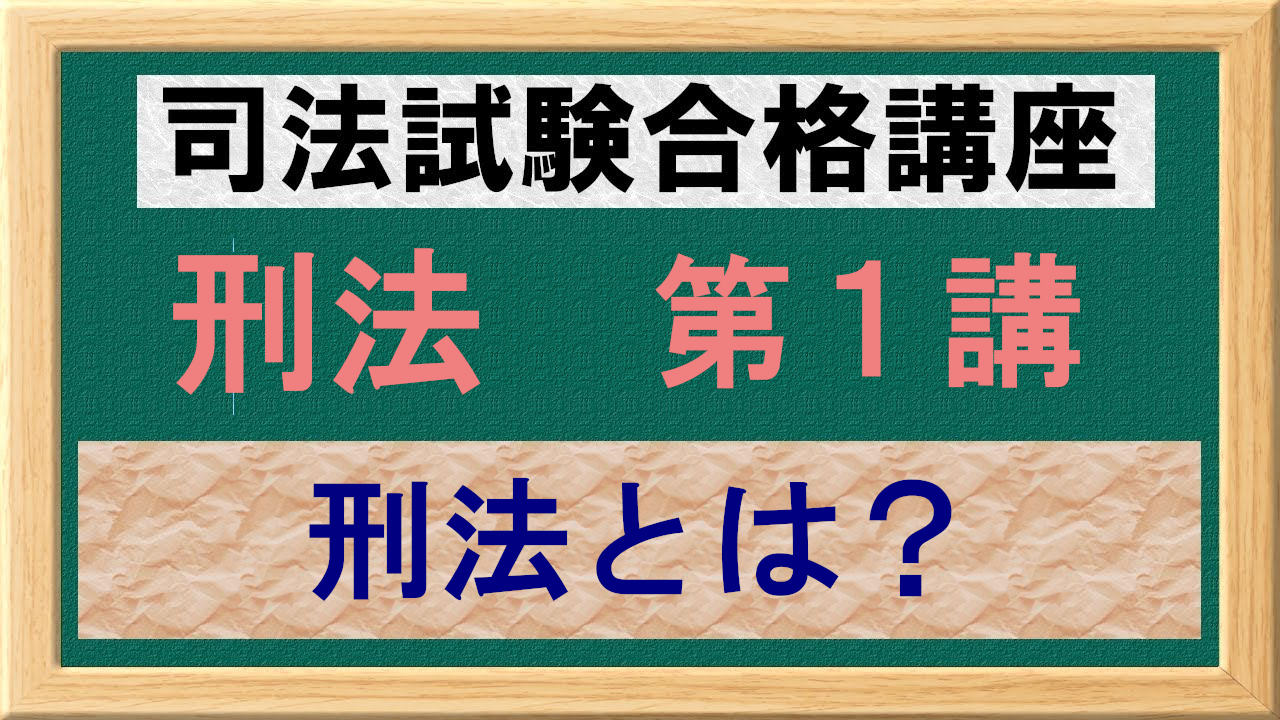・刑法の学習
① 刑法の学習上の特徴:入りずらく、出やすい
(1) 入りずらい =専門用語が多い ⇒ それを覚える
(2) 出やすい =論文の答案が書き易い ⇒ 体系が明確。順序を間違えずに書く
② 学習内容:犯罪について
刑法総論:どの様な場合に犯罪となるか ⇒ 刑法の基本原理・犯罪・罪数
刑法各論:どんな場合に何罪になるか ⇒ 個人的法益・社会的法益・国家的法益 に対する罪
第一編 刑法の基本原理
第1章 刑法の意義
1 刑法とは
・刑法:何が犯罪となるか及びその犯罪に対しいかなる刑罰が科せられるかを定めた法規
(例)199:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する
⇒ ~した者は=犯罪 ~に処する=刑罰
① 刑法の分類
形式的意義の刑法 :刑法と記された法規。 (例)刑法
特別刑法 :刑法と記されないが犯罪と刑罰を定めた法規。 (例)軽犯罪法、道路交通法
② 自然犯と法定犯
自然犯:道徳的に悪い犯罪 (例)殺人罪
法定犯:道徳的には無色又は無色に近いが行政等の必要上犯罪 (例)ゴールド免許で無免許運転
③ 刑法の機能
(1) 法益保護機能:法益=法的に保護される利益。生命・財産等 ⇒ 事前に威嚇・事後に制裁
・保護法益:ある条文が保護しようとしている利益≒趣旨
(2) 自由保障機能:犯罪となる行為を明示 ⇒ 犯罪でない行為を明示
⇒ ⑴=できるだけ成立 ⑵=できるだけ不成立 この判断の蓄積を学ぶ
2 刑法理論
① 犯罪の本質:犯罪に対する評価。人間存在の考え方と関連
決定論 :全て事前に決定 ∵ 善人と悪人から必然 ⇒ 主観主義:内面にある危険性
非決定論 :自由意思により選択 ∵ 人は皆危険性あり ⇒ 客観主義:外部に現れた結果
② 刑罰理論:刑罰の正当化根拠
(1) 応報刑主義 :当然の報い ⇒ 相応な刑罰を科すべき
(2) 一般予防主義 :一般人を威嚇 ⇒ 犯罪予防
(3) 特別予防主義 :再犯を防ぐため ⇒ 隔離・教育をすべき
| 人間の考え方 | 犯罪の本質 | 刑罰理論 | |
| 新派=近代学派 | 決定論 | 主観主義 | 特別予防主義 |
| 旧派=古典学派 | 非決定論 | 客観主義 | 一般予防主義・応報刑主義 |
③ 通説:相対的意思自由論=古典学派+近代学派
素質と環境との制約を受けながら ⇒ 特別予防主義
主体的に決定する自由意思を有する ⇒ 一般予防主義・応報刑主義 ∵ 客観主義が基本