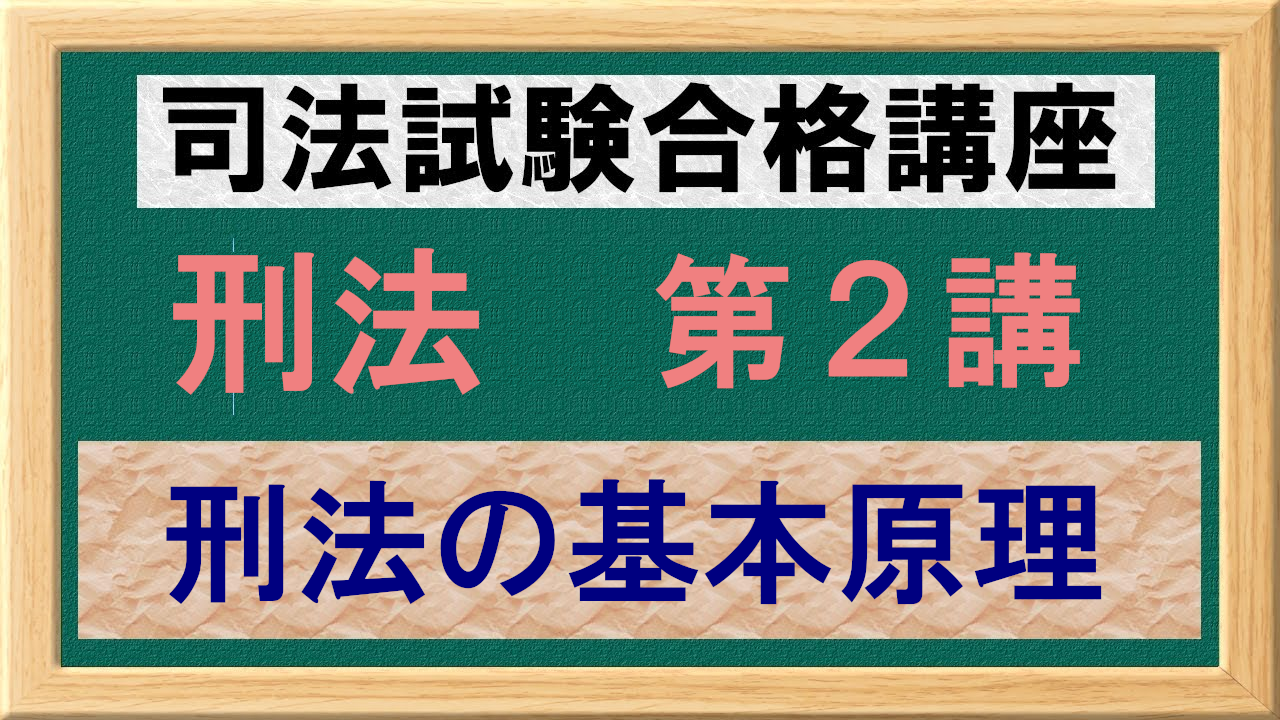第二章 刑法の基本原理
1 罪刑法定主義
① 意義:犯罪となる行為及びその刑罰についてあらかじめ成文の法律をもって規定しなければならない
⇒ 憲法31(適正手続き)・39(遡及処罰の禁止)・73⑥が根拠
② 内容
(1) 罪刑の法定:成文法主義。犯罪と刑罰を成文の法律で規定∵定義
×絶対的不確定刑-刑種・刑罰定めない (例)刑罰を科する・懲役に処す
〇相対的不確定刑-刑種・刑量の上限・下限を定める (例)1年以上、5年以下の懲役
+ 相対的不定期刑-上限・下限を定めて宣告 (例)3年以上、5年以下の懲役と宣告する刑
(2) 遡及処罰の禁止:あらかじめ。行為後に定められた規定を遡及的に適用不可∵定義
⇒ 憲法39。犯人に有利なら可6
(3) 類推解釈の禁止:犯人に不利益な類推解釈は禁止∵解釈
⇒ 犯人に有利なら可 + 犯人に不利益でも拡張解釈は可
2 刑法の適用範囲
時間的適用範囲
・原則、施行後 + 遡及処罰の禁止(犯罪でない行為や重い新法を適用すると罪刑法定主義違反)
① 6条の特則:犯罪後に刑が軽く変更 ⇒ 軽い刑を適用 ∵ 犯人に有利なので罪刑法定主義に反しない
- 犯罪後:実行行為終了後 ⇒ 実行行為の途中で法律変更なら6の適用なし=当然に新法
② 刑の廃止:裁判時までに刑が廃止 ⇒ 処罰できない(刑訴337②)但し、経過規定
場所的適用範囲
① 国内犯
(1) 属地主義(場所に着目):日本国内なら内容を問わず適用1
⇒ 国外にある日本船舶又は日本航空機内は日本国内と同様1Ⅱ
② 国外犯
(1) 属人主義(主に犯人の国籍に着目):日本人が一定の重大な罪を犯した場合3
⇒ 過失犯と単純横領罪を含まない
(2) 消極的属人主義(主に被害者の国籍に着目):日本人が一定の重大な犯罪の被害者となった場合3の2
(3) 保護主義(保護法益に着目):国益を害する一定の重大な罪
⇒ 日本国公務員が(国籍は問わない)一定の重要な職務犯罪を犯した場合4に適用+not属人主義